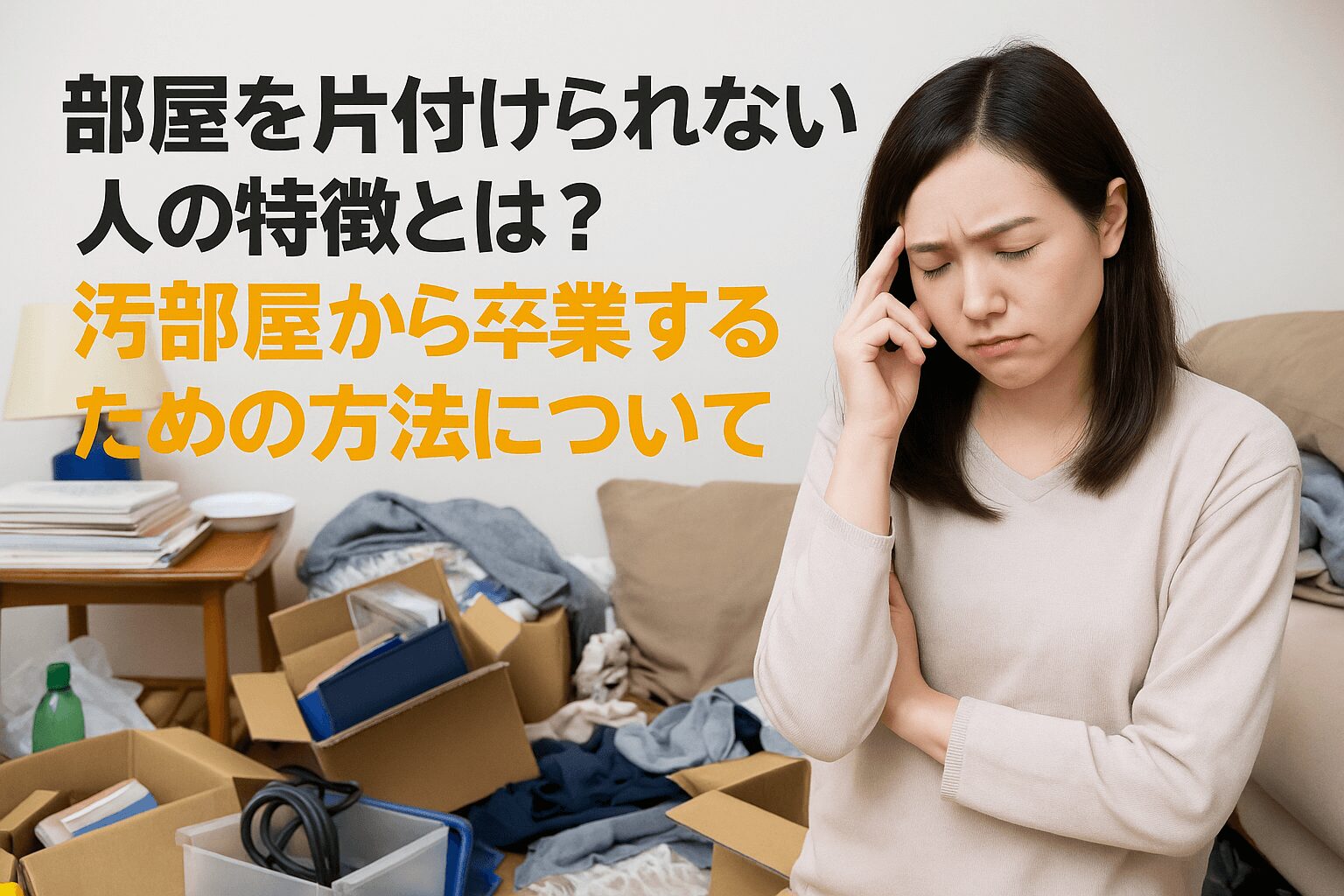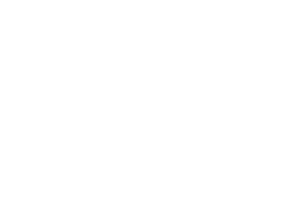気づけば部屋がモノで溢れ、どこから手をつけて良いか分からない状態になっていることなどありませんか?
来客の予定が入るたびに焦り、「どうして自分はこんなに片付けられないんだろう…」と自分の部屋に自信が持てない方なども多いでしょう。
実は、部屋が片付けられないことには、明確な理由と解決策があります。
ここでは、部屋が片付けられない人の特徴や心理に深く迫り、汚部屋から脱出するための最短ルートと、二度と汚部屋に戻らないための再発防止策を解説していきます。
なぜ部屋が片付かないのか?その原因と心理的特徴
部屋が散らかってしまう原因は、人それぞれ異なります。
片付かない原因には、環境や習慣が起因している場合と心理的な問題がある場合とがあります。
人それぞれ様々な要因が絡みあうことで大きな要因となっていきますが、多くの人に共通する心理や行動パターンなどもあり、それを学ぶことで原因を探ることができます。
以下では、それぞれよく見られる原因や特徴について詳しく見ていきましょう。
部屋が片付かない環境・習慣的原因とは
部屋が片付かない環境・習慣的原因には以下のようなものがあります。
不要なものが多すぎる
部屋が片付かない大きな原因としては、不要なものが多すぎる事にあります。
使用していないモノや「修理すれば使えるかも」と思うものなど捨てずに置いておくことがよくあります。
使用できるモノと機能を果たすモノの考え方は別次元なので、本当に今必要なのかをよく考える必要があります。
一般的には、半年使用しないモノは必要ないなどと言われるので、定期的に見直す必要があります。
部屋の片付ける習慣が無い
部屋を片付けられない方の多くは、日頃から部屋をキレイに片付ける習慣がありません。
ゴミはゴミ箱に捨てることすら後回しにして、後で捨てるからという考えでその辺に置いておくことが片付かなくなる原因になります。
また、何となく空いているスペースに荷物などを置いたりすることでも少しずつ部屋を散らかしていきます。
時間的余裕がない
日々の仕事や家事に追われて忙しい方などは、時間的余裕がなく休日も疲れて休んでしまうなどして片付けられなくなります。
片付けるにも多くの時間と体力を消費するので、自分で片付けられない方は人に頼むなどして片付けるようにしないとどんどん部屋を散らかすことになります。
部屋が片付かない方の心理的特徴とは
部屋が片付かない方の心理的特徴には以下のようなものがあります。
モノを捨てることに強い抵抗がある
「いつか使うかも」「もったいないから捨てられない」という気持ちが強い方は、なかなかモノを捨てられません。
特に、プレゼントでもらったモノや高かったモノ、思い出の品などは、捨てることに罪悪感を抱きがちです。
しかし、この「もったいない」という気持ちが、部屋にあるモノを処分する感情を妨げ、部屋のモノをどんどん増やしていく原因となります。
モノの「定位置」が決まっていない
使ったモノをどこに戻せばいいか明確に決めていない場合には、直す場所が分からないためにとりあえずその場に置きっぱなしにしてしまうことがあります。
一般的にこれが散らかりの始まりになります。
特に、郵便物やDM、文房具、充電コードなど、小さなモノほど散らかりやすく、気づけば机の上や床がモノで埋め尽くされてしまいます。
完璧主義で片付けを「一気にやろう」とする
「どうせやるなら徹底的に!」と意気込んで片付けを始めますが、あまりのモノの多さに圧倒され、途中で挫折してしまいます。
片付けは精神的にも肉体的にもエネルギーを消耗する作業です。
完璧を求めすぎることで、結局何も手につかなくなることが汚部屋化を加速させる大きな要因です。
疲労や精神的なストレスを抱えている
仕事や人間関係で疲れていると、片付けをする気力や体力がわきません。
また、孤独感や喪失感を溜め込んだモノで埋めようとする心理的な側面もあります。
部屋の乱れは、心の状態を映し出す鏡なのです。
汚部屋を卒業するための最短ルート:片付けは「思考」と「行動」の習慣化

汚部屋を片付けるための最も重要なステップは、「片付けに対する考え方を変える」ことです。
完璧を求めず、小さな一歩から始めることが成功への鍵となります。
具体的に汚部屋を卒業するための方法としては、以下のような方法を試してみましょう。
ステップ1:目標設定とスケジューリング
まず、「いつまでに」「どこを」「どんな状態にしたいか」を具体的に決めます。
例:「今週末までに、玄関の段ボールをすべて片付ける」
一度に家全体を片付けようとすると、途中で体力や気力が尽きて挫折しやすくなります。
まずは玄関や机の上など、小さなエリアから始めるのがおすすめです。
目標を明確にして達成しやすくすることで、やり切るモチベーションを維持しやすくなります。
モチベーションを保ったまま、少しずつ掃除をする範囲を広げると良いでしょう。
ステップ2:とにかく「ゴミ」を捨てる
片付けの第一歩は、誰の目から見ても明らかなゴミを捨てることです。
明らかなゴミの一例としては、以下のようなものになります。
- 賞味期限切れの食品
- 読まなくなった雑誌や古新聞
- 破れたビニール袋
- 壊れた家電や日用品
これらは「いる・いらない」の判断が簡単なので、思考停止で捨てられます。
ゴミ袋を複数用意し、可燃ゴミ、プラスチックゴミなど、分別しながらどんどん袋に入れていきましょう。
必要のないものを処分する作業だけで、部屋は驚くほどスッキリします。
ステップ3:モノを「仕分け」する3つのボックス
次に、ゴミを捨てた後のモノを「3つのボックス」に仕分けます。
| いるモノ | 今後も使う可能性のあるモノ |
|---|---|
| いらないモノ | 捨てるモノ(ゴミ以外のモノ) |
| 迷うモノ | 捨てるか迷っているモノ |
いるモノは、当然使用している必要な製品などになるので捨てる必要はありません。
一方で、いらないモノは迷わず捨てましょう。
いらないモノを不必要に保有しておくことがゴミを溜める要因になります。
迷うモノは、無理に今すぐ判断する必要はありません。
専用のボックスに入れて、1ヶ月など期限を決めて保管しておきます。
その期限を過ぎても開けなかったら、それは「なくても困らないモノ」だと判断し、思い切って手放しましょう。
ステップ4:モノの「定位置」を決める
モノを仕分けたら、それぞれの「定位置」を決めます。
これは片付けの再発防止に最も重要なステップです。
前述でも解説しましたが、どこに何をおくか決めておくことで無駄な散らかりを防止します。
使う場所の近くに置く
リモコンや充電器、文房具など、よく使うモノはすぐに手が届く場所にまとめて収納するとよいでしょう。
収納場所をあらかじめ決めておくことで、探す手間も省くことができます。
立てる収納を活用する
本や書類はついつい横に積み重ねてしまいがちです。
これを立てて収納することでどこに何があるか一目で分かり、出し入れがスムーズになります。
見せる収納と隠す収納を使い分ける
好きなモノは「見せる収納」でご自身の満足度を上げ、生活感の出るモノは逆に「隠す収納」にすると部屋が綺麗に片付いて見えます。
見せる収納と隠す収納を使い分けることで、部屋が非常におしゃれな空間に見えます。
ステップ5:プロの技を借りるという選択肢
「どうしても自分では片付けられない」「一気に片付けてしまいたい」という方は、プロの力を借りるのも一つの方法です。
整理収納アドバイザーや不用品回収業者に依頼することで、短時間で劇的に部屋をキレイにすることができ、部屋を整理整頓することができます。
プロと一緒に片付けることで、片付けのノウハウを学ぶこともできます。
汚部屋に二度と戻らないための再発防止策

一度部屋がきれいになっても、習慣が変わらなければまたすぐに汚部屋に戻ってしまいます。
きれいな状態をキープするための、簡単な習慣を身につけましょう。
「ワンイン・ワンアウト」の法則
欲しいモノを必要なだけ購入すると、使えるモノではありますが家の中に荷物が過剰に増える事になります。
新しいモノを1つ買ったら、古いモノを1つ手放すのようにルールを決めることで不必要なものを整理することができます。
このルールを徹底することで、モノが無駄に増えすぎるのを防げます。
5分間片付け習慣
毎日たった5分でいいので、片付けをする時間を作りましょう。
「朝、出かける前に床に落ちているモノを拾って定位置に戻す」ということや、「夜、寝る前に机の上をリセットする」など、少しでもよいので片付ける習慣をつけることで意識が変わります。
小さな習慣を長く続けることで、部屋の散らかりがひどくなる前に食い止めることができます。
「床にモノを置かない」ルール
床にモノを置くと、散らかっている印象が強くなります。
散らかっている状態に慣れてしまうと、徐々にゴミが放置されている箇所が増えてしまいます。
床にモノを置かずに床面積を広く保つことを意識するだけで、部屋がすっきりと見えて掃除もしやすくなります。
ゴミ出し日の確認と徹底
ゴミ出し日をカレンダーに書き込み、毎週必ずゴミを出す習慣をつけましょう。
ゴミが溜まると片付けへのモチベーションも下がり、すべてが後回しになってしまいます。
また、ゴミ袋がいっぱいに溜まってしまってから出そうなど考えている際にも、ゴミ捨てのタイミングを逃してゴミが溜まることを促進してしまうことがあるので注意が必要です。
まとめ
部屋が片付けられないのは、決してあなただけの悩みではありません。
しかし、その悩みを解決するための一歩は、間違いなくあなたの「行動」から始まります。
前述で紹介した「ゴミを捨てる」「モノの定位置を決める」「再発防止の習慣を身につける」という3つのステップを、ぜひ今日から実践してみてください。
完璧を求めず、焦らず、小さな成功体験を積み重ねていくことが、汚部屋からの脱出、そして自信と心の余裕を取り戻すための最短ルートです。
「どうしてモノを捨てられないんだろう?」「もっと効率的な収納方法はないかな?」などのようにお悩みの場合には、ひとりで悩まないで知人や友人の他に不用品回収専門業者などに頼ってみるのも良いかもしれません。
「片付けコミット」では、具体的な片付け方法やさらに深い心理的な側面についてなど知りたいことがあれば全力でサポートします。
不用品の買取にも強いので、不用品回収費用を抑えることも出来るので部屋の片付けで悩んでいる方は一度ご連絡だけでもしてみてはいかがでしょうか。