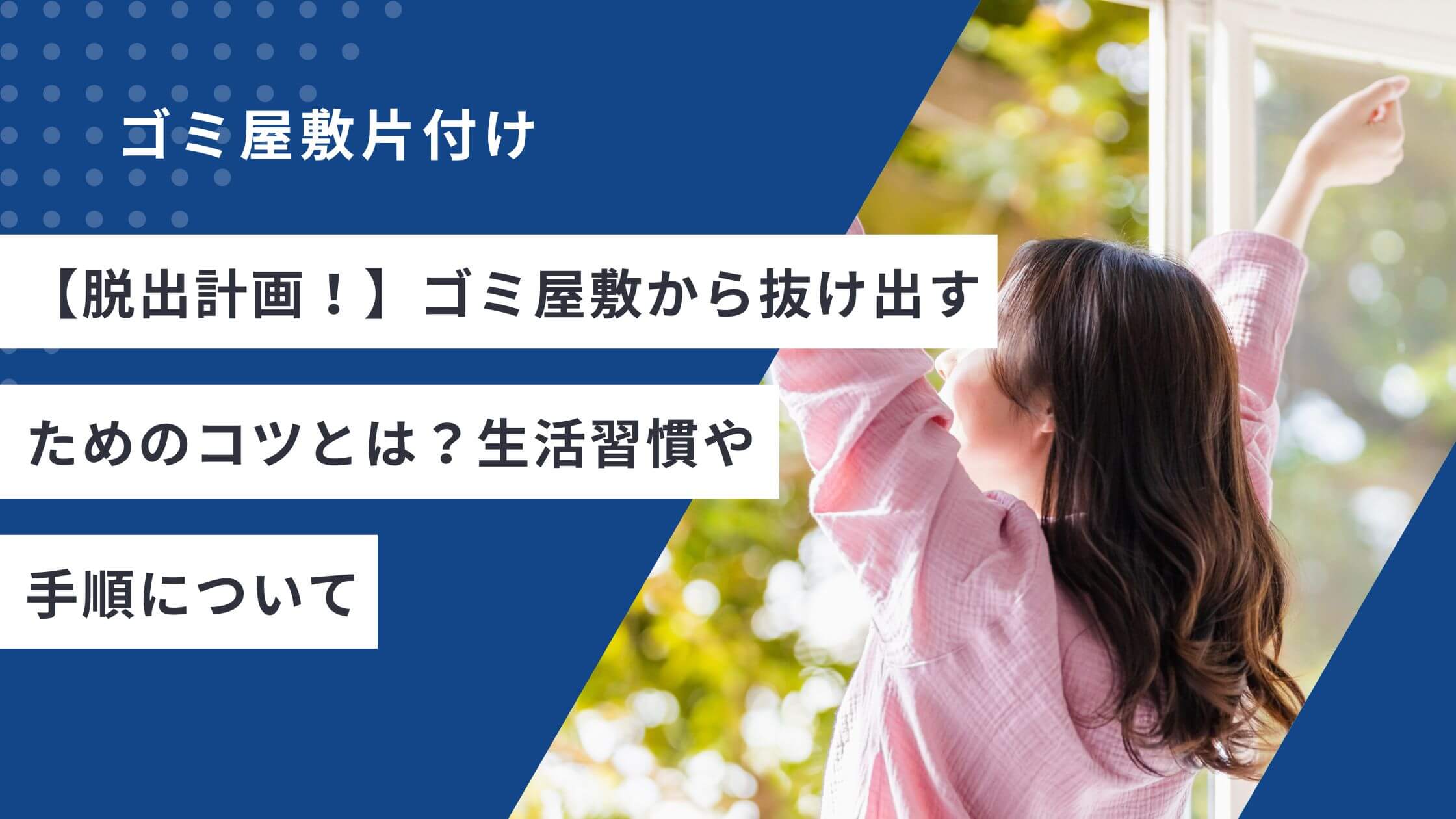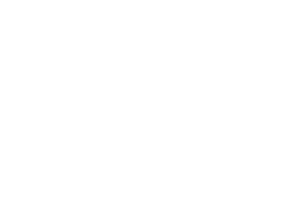ゴミ屋敷と聞くと大抵の方が他人事のように思うでしょう。
しかし、仕事や家事に追われて片付けが後回しになったり、気が付かないうちに物が増えたりして、誰でも簡単にゴミ屋敷化してしまう可能性があります。
そこで、この記事ではゴミ屋敷から抜け出すための具体的な方法や掃除の手順、生活習慣の見直し方など日常で意識しておきたいポイントを分かりやすく解説します。
ゴミ屋敷を何とかしたい方、無理なく片付けを始めたい方はぜひ参考にしてみてください。
目次
ゴミ屋敷とは
ゴミ屋敷とは、生活空間に大量のゴミや不用品が溜まり、日常生活が困難になっている家のことを言います。
一見、だらしなさや性格的な問題ととらえられがちですが、背景にはストレス・うつ・孤独・経済的な困窮などさまざまな要因が絡んでいることも多いです。
ゴミ屋敷には以下のような特徴があります。
- 床が見えないほどゴミや物が溜まっている
- 悪臭や害虫が発生している
- トイレ・キッチンなどが使えない
- 寝る場所がない
- 住人自身もどうすべきか分からない状態が続いている
ゴミ屋敷の問題を深刻化させないためにも、早めの対処と家族や友人による周囲の協力や理解が必要です。
ゴミ屋敷になってしまう要因

ゴミ屋敷は単なる片付けられないという問題ではなく、さまざまな背景があります。
ここではゴミ屋敷になってしまう主な要因を6つ解説していきます。
- 仕事や家事などで忙しい
- ストレスが溜まっている
- 物を捨てられない
- 衝動買いしてしまう
- 掃除や整理整頓が苦手
- 孤独を感じている
仕事や家事などで忙しい
毎日の仕事や家事などで忙しく、片付けや掃除に時間を割けないという人は少なくありません。
「今日は疲れているから明日にしよう」と先延ばしにしているうちに、気が付けばゴミ屋敷化してしまうというケースも多いです。
先延ばしにするとさらに掃除が大変になるので、こまめに片付ける意識を持つことが大切です。
ストレスが溜まっている
強い不安やストレスを抱えていると心の余裕がなくなり、掃除や整理整頓ができなくなることがあります。
また、片付いていない部屋にいること自体がストレスになり、さらに落ち込んでしまうという人も少なくありません。
部屋が散らかっていても気にならない、もしくは何もする気が起こらないという状態になっている場合は、一度かかりつけ医に相談してみましょう。
物を捨てられない
物を捨てられない、捨てることに抵抗があるという人はゴミ屋敷化しやすいです。
「いつか使うかも…」「高かったしもったいない…」という気持ちで、不要品やゴミを捨てずに溜め込んでしまう人は物が増え続けてしまいます。
部屋を美しく保つためには、不要な物を処分して物を増やしすぎないことが大切です。
衝動買いしてしまう
セールや広告の品などに釣られて衝動買いしてしまう人も注意が必要です。
必要がない物でも安いから、お得だからという理由で買ってしまい、それが積み重なると部屋に物が溢れてしまいます。
物を購入するときは収納場所まで決めてから、計画的に行うことが大切です。
掃除や整理整頓が苦手
そもそも掃除や整理整頓が嫌いな人や苦手な人はゴミ屋敷化しやすいです。
どこから手を付ければよいか分からないという人は、片付けや掃除そのものが嫌になってしまいます。
その結果、部屋が散らかっている状態が当たり前になり、ゴミ屋敷化してしまうことがあります。
孤独を感じている
一人暮らしや高齢者などで孤独を感じている人は生活に対する関心が薄れ、掃除や片付けをしなくなってしまうことがあります。
「どうせ一人だし片付けなくていいや…」という気持ちになり、片付けが後回しになってしまうという人も少なくありません。
また、孤独を埋めるために物を増やしてしまうという人もいます。
ゴミ屋敷を放置することのリスク

ゴミ屋敷は見た目の問題だけでなく、健康・安全・さらには法的なリスクにもつながる可能性があります。
ここでは、ゴミ屋敷を放置することの主なリスクを5つ解説します。
- 悪臭がする
- カビや害虫による健康被害
- ご近所トラブルの発生
- 火災の発生
- 強制撤去の可能性も
悪臭がする
食べ残しやカビ、汚れた衣類などが溜まると強い悪臭を発するようになります。
最初は部屋の中だけでも、徐々に玄関やベランダ、窓から外に臭いが漏れ出しししまうことも多いです。
特にマンションやアパートなど集合住宅では、周囲の人に迷惑をかけてしまい、苦情やトラブルの原因になるケースも少なくありません。
カビや害虫による健康被害
ゴミ屋敷は物が多いため湿気が溜まりやすく、カビ・ダニ・ゴキブリ・ハエ・ネズミなどの害虫や害獣が発生しやすい環境にあります。
これらは喘息やアレルギー、食中毒や皮膚炎などの健康被害を引き起こす可能性があります。
また、ゴミを放置すると菌やウイルスが繁殖しやすくなり、免疫が低下した高齢者や子どもには特に危険です。
ご近所トラブルの発生
ゴミ屋敷は見た目の不快感だけでなく、悪臭や害虫の発生などにより周囲に影響が及び、近隣住民とのトラブルを招くことがあります。
迷惑を感じた近隣住民から自治体や管理会社へ通報されるケースも少なくありません。
ゴミ屋敷がきっかけで要注意物件として扱われ、住み続けることが難しくなってしまうこともあります。
火災の発生
ゴミや物が積み重なっている状態では、火災のリスクが高まってしまいます。
特に紙類、衣類、プラスチック類などの燃えやすい物が積もることで、小さな火種から大きな火災へと繋がってしまうケースも多いです。
また、物で溢れた部屋ではもしも火災が発生しても、逃げ遅れてしまう可能性が高くなります。
強制撤去の可能性も
ゴミ屋敷状態があまりにも長く続くと、近隣住民からの通報や苦情を受け自治体が介入することがあります。
状況によっては強制的に片付けが行われたり、強制退去を命じられたりするケースもあります。
ゴミ屋敷が原因で自宅を失ってしまう可能性があるということを知っておきましょう。
ゴミ屋敷から抜け出すためのコツ

ゴミ屋敷を片付けたいと思ってもどこから手を付ければ良いのか分からないという人は多いです。
ここでは、ゴミ屋敷から抜け出すための具体的な方法や考え方を紹介します。
一人で悩まずに現実的にできることから始めてみましょう。
- 自分の部屋の状態を客観視する
- まずは「片付ける」ことを決める
- スケジュールや目標を設定する
- 自分だけで片付けられるか見極める
- 家族や友人に相談して手伝ってもらう
- 自分でできない場合は片付け業者に依頼する
自分の部屋の状態を客観視する
ゴミ屋敷化している状態に慣れてしまうと、どれだけ散らかっているかということに気が付きにくくなります。
そんな時は、スマホなどで自分の部屋を写真に撮って、客観的に見てみましょう。
写真などで客観的に見ることで、今の部屋の状態に気が付き、片付けたいという気持ちが湧いてくることがあります。
片付けを成功させるためには、まず片付けたいという気持ちになることが大切です。
まずは「片付ける」ことを決める
ゴミ屋敷を片付けるための最初の一歩は片付けを決意することです。
どれほど部屋が散らかっていても、住人自身が片付けたいと思わなければ何もスタートしません。
片付けるのが面倒、何をすればよいか分からないと感じるかもしれませんが、まずは片付けるという強い意志を持つことが大切です。
スケジュールや目標を設定する
ゴミ屋敷の片付けを自分でする場合は一日で終わらせるのは難しいです。
そのため、いつまでに、どれくらい、どんなペースで片付けるかという具体的なスケジュールを組みましょう。
今日は玄関だけ、明日はキッチンというようにスペースごとに区切って目標を設定することが大切です。
自分だけで片付けられるか見極める
ゴミの量や部屋の広さ、作業にかかる時間を考えて、自力で片付けられるかどうかを冷静に判断しましょう。
無理をしてさらに片付けが嫌になったり、途中で投げ出したりしてしまうと逆効果です、
特に高齢の方や、体力に自信がない方は安全面を考えても一人で掃除をすることはお薦めできません。
一人で掃除をするのが難しいと感じたら、周囲の人に相談してみましょう。
家族や友人に相談して手伝ってもらう
自力で掃除をするのが難しいと思ったら、家族や友人など信頼できる人に相談して手伝ってもらうのがおすすめです。
まずは自分一人で問題を抱え込まずに、周囲の人に相談すれば精神的にも身体的にも負担が軽くなります。
第三者の目が入ることで不用品の分別もかなりスピードアップすることが多いです。
自分でできない場合は片付け業者に依頼する
自分だけで片付けるのが難しい、周囲の人に相談するのも嫌、と言う場合は片付け専門業者に依頼するのがおすすめです。
専門業者は片付けのプロなので、短時間で効率的に部屋を綺麗にしてくれます。
多少費用はかかりますが、一気に部屋をリセットできるのは大きなメリットです。
業者を選ぶ際は、複数業者から見積もりを取り、信頼できる業者を選びましょう。
ゴミ屋敷を自分で片付けるための掃除の手順

一度ゴミ屋敷化してしまうとどこから手を付けたらよいか分からないというのが正直な気持ちではないでしょうか。
しかし、順番に一つずつ進めていけば、少しずつ部屋は美しくなっていきます。
これから紹介するステップを参考に、無理のないペースで進めていきましょう。
- 片付ける場所を決める
- 床に落ちているゴミを捨てる
- 必要な物と不必要な物を分ける
- 必要な物を片付ける場所を決める
- 整理整頓をする
- 清掃をする
1.片付ける場所を決める
いきなり全部を片付けようとすると途中で挫折してしまうことが多いです。
まずは玄関や廊下、寝室、キッチンなどスペースを区切って片付ける場所や順番を決めましょう。
今日はこの部屋だけといった具合に無理のない範囲を設定することで、片付けを嫌にならずに続けることができます。
2.床に落ちているゴミを捨てる
片付けるエリアを決めたら、最初に床に散乱している明らかなゴミを拾って捨てましょう。
食べ残しの容器、コンビニの袋、使い終わったテッシュなど、見てすぐにゴミだと分かる物からゴミ袋に入れていくことが大切です。
ゴミを拾うだけでも部屋の印象は大きく変わります。
ゴミ袋を複数用意して、燃えないゴミと燃えるゴミに分別していくと効率的です。
3.必要な物と不必要な物を分ける
ゴミを捨てたら次に残っている物の仕分けを行います。
仕分けの際には、よく使う物、あまり使わないけど必要な物、めったに使わない物の3つに仕分けるのがポイントです。
めったに使わない物は一つの箱などに入れて1年間保管し、1年後に使わなかった場合は処分するという方法がおすすめです。
4.必要な物を片付ける場所を決める
物の仕分けが終わったら、必要な物を片付ける定位置を決めましょう。
例えば、文房具は引き出しに、衣類はクローゼットに、リモコンはテレビ台に、など使いやすく片付けやすい場所を選ぶのがポイントです。
物の定位置が決まると、次に使った時に自然と戻す習慣がつき、部屋が散らかりにくくなります。
定位置が決まったらラベルを貼って分かりやすくするのもおすすめです。
5.整理整頓をする
物の定位置が決まったら、その場所にそれぞれ収納します。
よく使う物は手の届く範囲に、たまに使う物は高い場所にしまうなど、使用頻度に応じた配置にすると生活がしやすくなります。
また、収納がいっぱいになったら新しい物を増やさないというルールを作ると、物が増えすぎないのでおすすめです。
6.清掃をする
最後に、床や家具の表面、キッチンやトイレなどの水回りを掃除します。
床にはほこりが溜まっていることが多いので、掃除機をかけてから雑巾がけをするのがおすすめです。
水回りはカビが生えていることが多いので、カビ取り洗剤を使いましょう。
片付けだけをしても目に見えないホコリやゴミはとり切れないので、最後に清掃をすることが大切です。
ゴミ屋敷を業者に片付けてもらうための手順

自力での片付けが難しい場合は、専門の片付け業者に依頼するのが効果的です。
ここでは、片付け業者に依頼するための具体的な手順を紹介します。
- 複数の業者で相見積もりを取る
- 依頼する業者を決める
- 依頼する範囲を決める
- 片付けの日程を決める
- 片付けをする
1.複数の業者で相見積もりを取る
片付け業者によって料金やサービス内容が異なります。
1社だけで決めてしまうと相場が分からずに高い金額で契約するリスクもあるため危険です。
まずは複数の業者から相見積もりを取り、金額と内容を確認しましょう。
見積もりは無料のところが多いので、その際に説明の分かりやすさやコミュニケーションの取りやすさを確認するのがおすすめです。
2.依頼する業者を決める
見積もりの料金・作業内容・対応の良さなどを比較して依頼する業者を選びます。
極端に安い業者の中には、作業後に高額な追加費用を請求する悪徳業者が含まれている可能性があるので注意しましょう。
契約前に不明な点を確認して、信頼できる業者に依頼することが大切です。
3.依頼する範囲を決める
業者が決まったら、次に依頼する範囲を決定します。
部屋全体を依頼するのか、もしくは一部の部屋だけ依頼するのか、など作業範囲を決めましょう。
また、貴重品は残して欲しい、衣類は捨てたくないなど細かな要望がある場合は事前に伝えておくことが大切です。
4.片付けの日程を決める
次に片付け業者と相談して作業日を決定します。
希望の日程がある場合は、なるべく早めに相談しましょう。
片付け作業には半日~数日かかることも多いので、無理のないスケジュールを設定することが大切です。
立ち合いが必要なケースが多いので、作業日は依頼者も予定を空けておきましょう。
5.片付けをする
いよいよ片付け作業がスタートします。
業者が到着したら作業の最終確認を行い、作業を始めます。
当日は一人~複数人のスタッフが効率的に片付けを進めてくれるため、短時間で部屋が美しくなることも多いです。
立ち合いが必要な場合が多いので、捨てたくない場所や触ってほしくない場所は、その都度指示しましょう。
自力で難しい場合は片付け業者を利用しよう
ゴミの量が多すぎたり、体力的・精神的に片付けが難しいと感じたりしている場合は、無理をせず片付け業者に力を借りるのがおすすめです。
業者に依頼すると多少費用は必要になりますが、短時間で効率的に部屋を美しく整えてくれます。
部屋が美しくなることで心身ともにストレスが減り、生活がしやすくなるので、一人で抱え込まずにプロに相談するのがおすすめです。
ゴミ屋敷を再発させないために見直すべき生活習慣とは

せっかく部屋を片付けても生活習慣が変わらなければすぐに元のゴミ屋敷に戻ってしまう恐れがあります、
ここでは、ゴミ屋敷を繰り返さないために意識したい5つの生活習慣を解説します。
- 使ったら元の場所の戻す習慣を身に付ける
- ゴミはすぐに捨てる癖をつける
- 収納場所を明確に決める
- 衝動買いをやめる
- 物を溜め込みすぎない意識を持つ
使ったら元の場所の戻す習慣を身に付ける
部屋が散らかる主な原因は「出しっぱなし」です。
使ったら必ず元の場所に戻すという基本的な習慣を身に付けましょう。
収納場所が決まっていれば片付けるのも簡単になり、探し物をする手間も減ります。
最初は面倒に思うかもしれませんが、意識して続けていくうちに習慣化するので、根気よく続けていきましょう。
ゴミはすぐに捨てる癖をつける
ゴミが出た時に後でまとめて捨てようと思って机や床に放置すると、ゴミがどんどん溜まってしまいます。
食べ終わった後の容器やチラシなどゴミはその場ですぐに捨てるという癖をつけましょう。
小さなゴミ箱を各部屋に置くと、ゴミを捨てることが習慣化しやすいのでおすすめです。
収納場所を明確に決める
物を片付けようと思っても収納場所が明確でないと床や机の上がすぐに散らかってしまいます。
それぞれの物に定位置を決めておくことで、整った部屋を維持することが可能です。
収納スペースが足りない場合は、不用品を処分したり収納グッズを見直したりしましょう。
衝動買いをやめる
「安いから」
「かわいいから」
「お得だから」
などといった理由で衝動買いばかりをしてしまうと、気が付かないうちに物が部屋に溢れてしまいます。
買い物をするときは計画的に行い、基本的に衝動買いはしないようにしましょう。
特に最近はインターネットで簡単に買い物ができるので、いったん考えてから購入を決めることが大切です。
物を溜め込みすぎない意識を持つ
日本ではもったいないという精神が定着しているため、物を捨てることを躊躇う人が多いです。
特に高かったから、いつか使うかもという理由で使用頻度が低い物を何年も溜め込んでいる人も少なくありません。
定期的に使っていない物を見直し、使っていない物は処分する気持ちを持ちましょう。
ゴミ屋敷化しないために普段からできること

美しい部屋を保つためには日々のちょっとした習慣がとても大切です。
ここでは、誰もが今日から実践できる部屋を整えるための工夫を紹介します。
- 毎日5分のリセットタイムを設ける
- 週1回整理整頓する日を設ける
- ゴミ捨てをしやすい仕組みを整える
- 定期的に物を断捨離する
毎日5分のリセットタイムを設ける
仕事や育児などで毎日忙しい人が多いとは思いますが、毎日5分でもよいので部屋を整える時間を作りましょう。
床に落ちているゴミを捨てる、散らかっている物を元の場所に戻すという簡単な作業をするだけでも十分です。
一気に掃除しようとせずに、毎日少しずつ部屋を整えることを習慣にするだけで美しい部屋を保つことができます。
週1回整理整頓する日を設ける
週に1回「整理整頓デイ」を設けるのもおすすめです。
例えば平日忙しい人は、休日にでもよいので整理整頓を行いましょう。
今日は冷蔵庫、今日は机の上、などその日によって整理整頓する場所を変えるとまんべんなく部屋を整えることができます。
家族がいる場合は、家族と一緒に行うことで家族みんなが片付ける意識を持つことができます。
ゴミ捨てをしやすい仕組みを整える
ゴミが捨てにくい環境だとつい後回しになって、床や机の上にゴミが溢れてしまいます。
リビングのよく座っている場所の近くにゴミ箱を置く、ゴミ袋を常にストックしておくなどゴミ捨てを習慣化できる仕組みを整えましょう。
また、ゴミの日をカレンダーに記入する、スマホで通知してくれるようにするなどすると、ゴミ捨ての日を忘れにくくなるのでおすすめです。
定期的に物を断捨離する
物が増えすぎると、すぐにゴミ屋敷化してしまいます。
そのため、定期的に持ち物の見直しをするのが大切です。
衣替えのタイミングや季節の変わり目などに使っていない物を捨てる機会を作りましょう。
1年以上使っていない物は捨てるなどのルールを決めると、断捨離も捗ります。
まとめ
ゴミ屋敷は誰にとっても無関係な話ではなく、心の状態や生活習慣次第で誰でもなる可能性があります。
もしもゴミ屋敷化してしまった時は、放置せずにできるところから片付けを始めましょう。
自分で片付けるのが難しい場合は、業者の手を借りるのもおすすめです。
片付けが終わった後は、元の状態に戻らないように生活習慣を見直すようにしましょう。
無理なく、自分のペースで片付けや掃除を続けていくことが大切です。