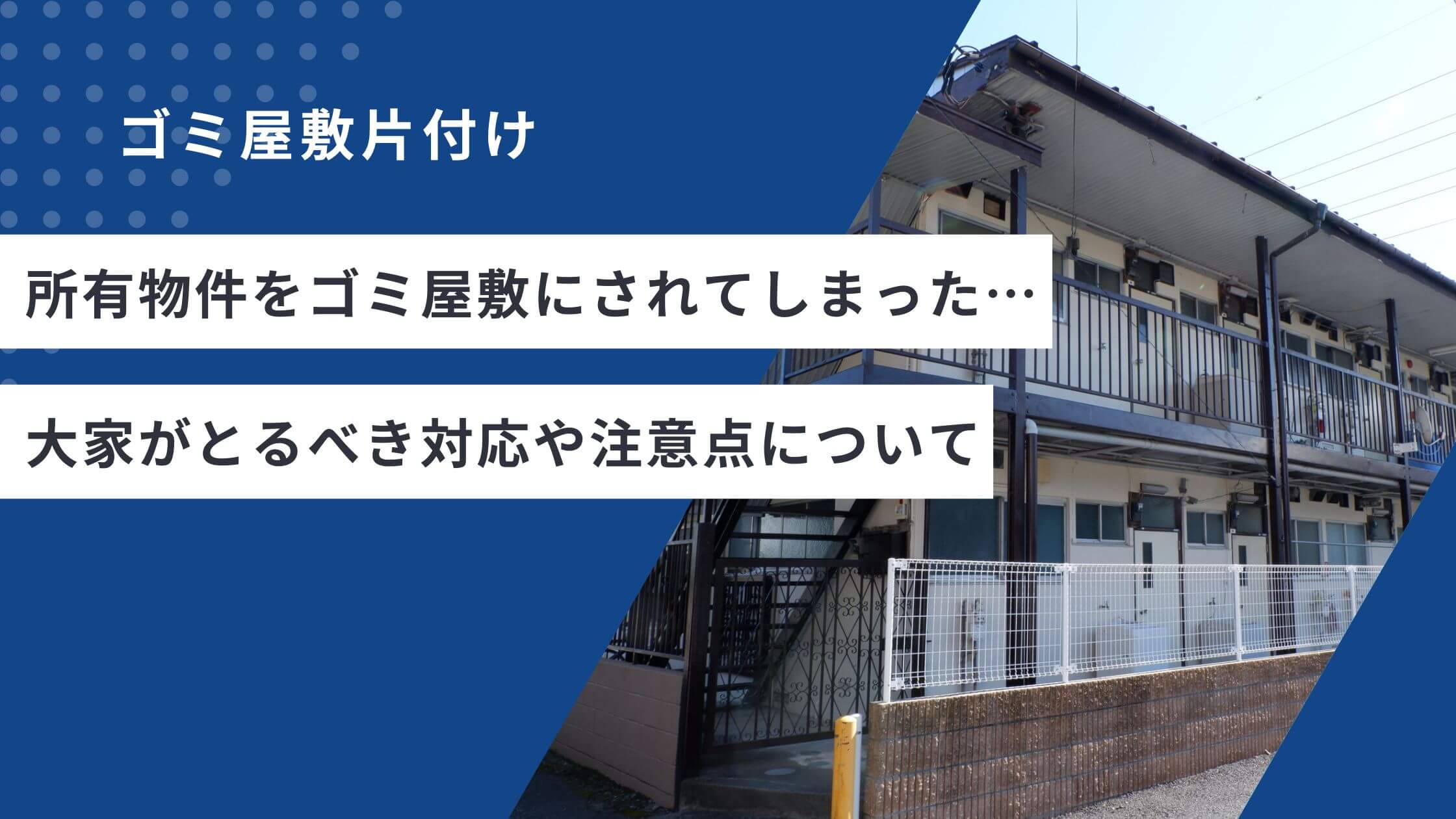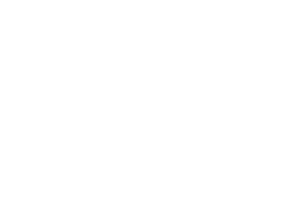自分が所有しているアパートなどの物件がゴミ屋敷にされてしまった時には、物件そのもののイメージに悪い影響を与える・原状回復のために多大なコストがかかる可能性があります。
ゴミ屋敷を放置することで、大家さんが被る損失は計り知れないと考えるべきです。
今回の記事では、自分の所有物件がゴミ屋敷化してしまった時に大家さんがとるべき対応や注意点について詳しくまとめました。
ゴミ屋敷問題に悩んでいるのなら、ぜひこの記事を参考にしてみてください。
目次
ゴミ屋敷の住人はなぜ家をゴミだらけにしてしまうのか?
まずは、ゴミ屋敷ができてしまう代表的な理由についてまとめました。
特に単身世帯の方が家をゴミだらけにする理由は、以下のようなものです。
- ストレスなどの理由によりうつ状態に陥っている
- 忙しくてゴミ出しの時間にゴミを捨てられない
- 物を捨てられない気持ちが強過ぎる
- アルコールなど何らかの理由で健全な生活が送れていない
- 認知症や体の病気でゴミ出し自体が困難
- ゴミ出しのルールやスケジュールを把握することができない・面倒
人間が生活していれば、ゴミは毎日増えていきます。
上記のような理由でゴミが全く出せない状態が続けば、簡単に家の中がゴミで溢れてしまうのです。
ゴミ屋敷の物件にあるリスク

ゴミ屋敷には、安全上・衛生上多くのリスクが存在します。
アパートなどの集合住宅や隣家と密着して建っている戸建てでは、よりそのリスクが周囲の人に迷惑をかけると考えてください。
害虫が発生する
生ゴミを放置すれば、ゴミからゴキブリ・ハエ・ウジ虫が増えてしまいます。
一度発生した虫はゴミ屋敷内に留まらず、近隣の住宅にも侵入する恐れがあるでしょう。
さらに、害虫の駆除には多くの手間がかかります。
悪臭が発生する
腐敗したゴミからは悪臭が発生します。
ゴミ屋敷の住人が窓や扉を閉めていても、その臭いは周囲に漏れ出すものです。
ゴミ屋敷から漂う悪臭のせいで、近隣の住人が窓を開けられなくなる・建物全体が臭ってしまう可能性があるでしょう。
悪臭は部屋に染み付くため、退去後の修繕に多くの労力が必要です。
火災が発生しやすくなる
ゴミ屋敷の住人はゴミを分別することもなく積み重ねていきます。
そのため、何らかの理由でゴミが引火した時に、ゴミを伝って他の住宅よりも早く火が燃え広がってしまうでしょう。
例えば、ゴミのせいで繁殖したネズミがコードをかじり、火花から引火するケースもあるのです。
もちろん火災の被害はゴミ屋敷のみでは留まらず、多くの部屋に甚大な被害をもたらします。
物件の倒壊リスクが高まる
ゴミ屋敷では、木材を腐食させる可能性が高くなります。
住宅にゴミが溢れて手入れがされない状態が続けば、ゴミに溜まった水分が住宅の床や壁に染み込んでいくのです。
腐食した木材はシロアリが繁殖しやすくなり、柱や床を食べて住宅の強度を下げてしまいます。
結果的に、建物全体の倒壊リスクが高くなると考えてください。
それでも大家さんがゴミ屋敷の家主を強制的に立ち退きさせるのは難しい

先ほどもお伝えしたように、ゴミ屋敷は大家さんにとって非常に大きなリスクです。
ゴミ屋敷の住人が近隣住人に迷惑をかけていても、日本の法律上では大家さんがゴミ屋敷の家主を強制退去させることは難しいと考えてください。
ゴミ屋敷の家主でも借主の権利が守られる
賃貸借契約を結んでいる以上、借主は契約書で守られています。
そのため、債務不履行など両者の信頼関係を著しく崩す正当な理由がなければ、契約を解除することが難しいのです。
大家さんが一方的にゴミの問題以外の過失がないゴミ屋敷の家主を立ち退かせることは、法律上許されていないと言えるでしょう。
ゴミ屋敷の住人に立ち退いてもらうために大家さんができること

法律上、強制退去をさせることは難しいですが、大家さんは次のようなアプローチでゴミ屋敷の家主に立ち退きを依頼できます。
お金と時間がかかるものの根気よく対応を続ければ、家主の気持ちを変えられる可能性があるでしょう。
1.電話や口頭で注意をする
まずは、電話や直接物件に出向いて本人にゴミの問題について注意します。
高圧的な態度をとらず、「近隣の方が困っている」「このように改善してほしい」というお願いベースを維持すると良いでしょう。
初めから信頼関係を崩すと、事態が悪化する可能性があるため注意してください。
2.管理会社を通じて話し合いの場を設ける
本人に注意喚起をしても状況が変わらなかった場合は、管理会社を通じて話し合いの場を設けます。
話し合いはあくまで任意であるため、ゴミ屋敷の家主を強制的に呼び出すことはできません。
一方的に解決を強制するのではなく、自治体の生活支援事業や片付けの専門業者を紹介するなどの方法で、ゴミの問題の改善に促しましょう。
3.管理会社から保証人・緊急連絡先に相談する
ゴミ屋敷の家主が話し合いに参加してくれない・話し合いをしても協力を得られないようであれば、管理会社から賃貸借契約時の保証人・緊急連絡先に状況を相談して問題の解決を依頼するという手もあります。
家主本人に問題を解決する気・能力が欠けているとしても、家族が主導でゴミ屋敷の改善を促してくれるケースも多いのです。
4.条例を確認して自治体に相談する
ここまでのステップを踏んでも問題が改善しない時には、物件がある自治体の条例を確認します。
自治体の中には、条例でゴミ屋敷に対する対応を定めているケースがあるのです。
自治体が協力してくれることになれば、市の職員がゴミ屋敷を訪問して住人に適切な指導をする・行政代執行という形で強制的な片付けを実施します。
自治体にある条例次第ですが、ゴミ屋敷は地域全体の問題につながると認識されているのです。
5.ゴミ屋敷の家主に内容証明郵便で通達を送る
自治体の協力を得られない場合や、それでも状況が改善しない時には、訴訟の準備を始めます。
まずは、以下のような内容の書面を作り、内容証明郵便でゴミ屋敷の家主に通達を送りましょう。
- 通達の趣旨
- 文書送付日時
- ゴミ屋敷の家主の氏名と住所
- 大家または管理会社の氏名と住所
- 弁護士など通知書作成代理人
- 賃貸借契約がある事実
- 通達書作成に至った経緯
- 家主に求める行動
- 家主に求める行動の期限
- 期限までに対応がなかった場合に、賃貸借契約解除などの対応をとるという説明
内容証明は自分でも作成できますが状況に合わせて文章を変更する必要があるため、弁護士に作成を依頼すると良いでしょう。
6.訴訟を起こす
内容証明を送って設定した期限を過ぎてもゴミ屋敷の状態が改善しない時には、次のような証拠を集めて訴訟を起こします。
- ゴミ屋敷のせいで発生している害虫などの被害の写真を撮影
- 外から見たゴミ屋敷の状態を撮影
- 共用部分などにゴミが溢れている様子を撮影
- 近隣十人の苦情をまとめた文章や音声データの作成
ただし、訴訟を起こしてもゴミ屋敷の住人に立ち退いてもらえるとは限りません。
訴訟では、原状回復費用と損害賠償費用を請求できます。
ゴミ屋敷の家主を立ち退きさせた裁判の事例
訴訟を起こしても、ゴミ屋敷の問題を解決できるとは限りません。
しかし過去には、裁判によりゴミ屋敷の家主の立ち退きが認められた事例もあります。
その事例では、以下の点がポイントになりました。
- 大家は消防署からゴミが原因で火災になる危険性があると注意を受けた
- 多数の近隣住人がゴミ屋敷に迷惑しており、大家が注意を続けたが状況が変わらなかった
- 2年以上もの間、住人は常識を越える量のゴミを放置し続けた
ゴミの量や借主の対応、さらに近隣への危険性が争点になったと言えるでしょう。
訴訟を考えている方は、過去の事例を調べてみると良いです。
ゴミ屋敷のトラブルを回避するために大家さんができること
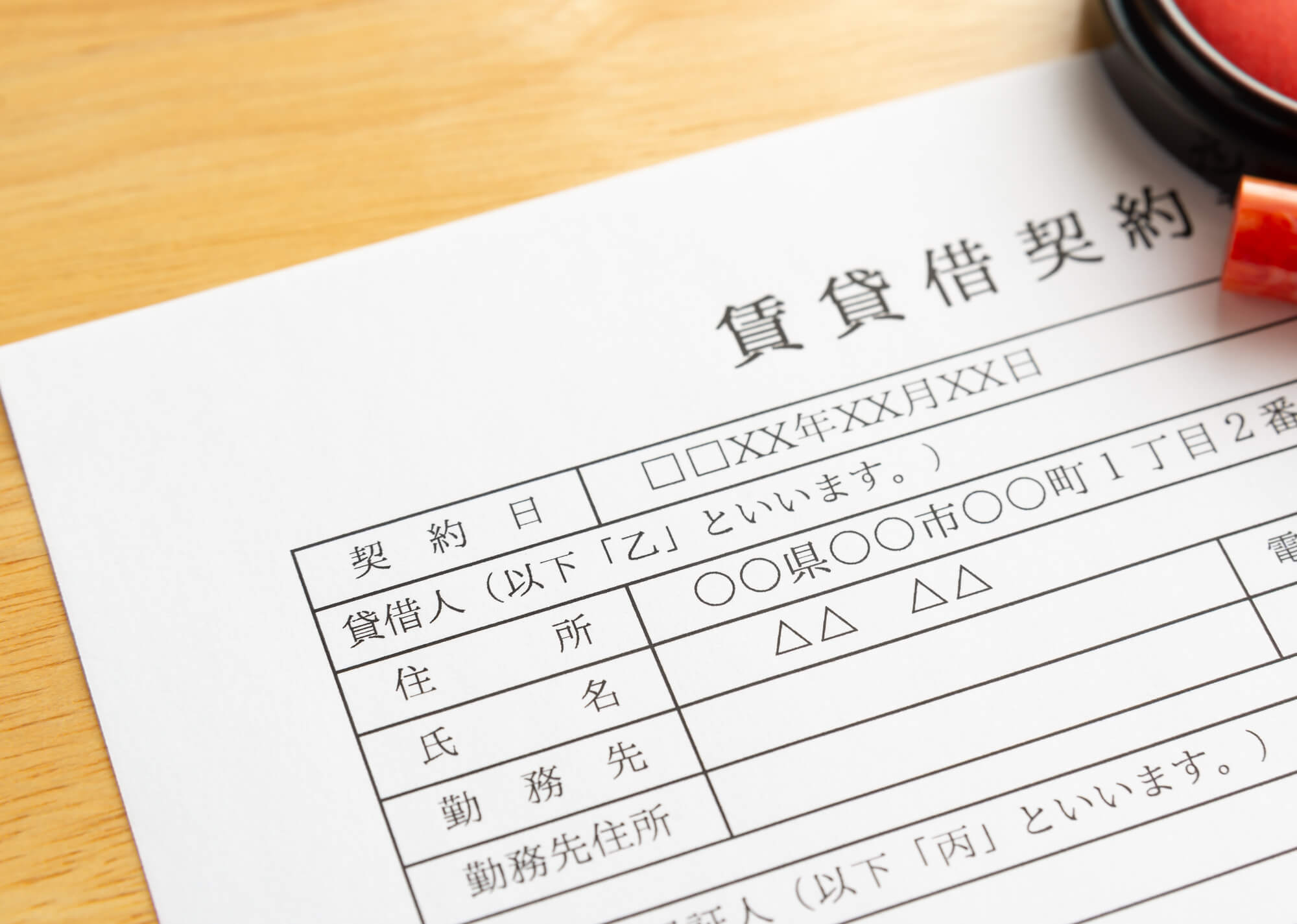
今後発生する可能性があるゴミ屋敷のトラブルを回避するためには、次のような取り組みが効果的です。
今後のトラブルを避ける目的で、効果的な取り組みを知っておきましょう。
賃貸借契約書で特約を結んでおく
賃貸借契約書に以下のような特約を追加すれば、物件をゴミ屋敷にされてしまった時に契約解除を進めやすくなります。
- 物件がゴミ屋敷になった場合は賃貸借契約を解除する
- ゴミの影響で発生した修繕費は家主の負担になる
- 安全性・衛生など、近隣の迷惑となる行為を禁止する
もちろん特約があってもスムーズにゴミ屋敷を改善できるとは限りませんが、入居者に対しての注意喚起になるでしょう。
定期的に物件の状態をチェックする
ゴミ屋敷は数日で完成するものではありません。定期的に物件の外観や共有部分を点検し、ゴミの蓄積・悪臭・害虫がないか調べましょう。
早い段階で問題に気がつけば、改善のハードルが低い状態で対応をとれます。
特に入居者が病気やケガのせいで健全な生活が送れなくなっている場合、必要なサービス・サポートにつなげられる可能性もあるでしょう。
住人がゴミ出ししやすい環境を用意する
「ゴミ出しができなかった」
「ゴミ出しのハードルが高い」
などの理由で少しずつゴミが蓄積されてしまうケースもあります。
例えば、夜勤の方や帰りが遅く朝の時間に余裕がない方にとって、ゴミ出しのハードルは高くなるものです。
初めは数袋だけゴミ出しができなかった状態が、徐々にゴミ出しが不可能な量になってしまい、結果的にゴミ屋敷化する事例も多いです。
24時間ゴミ出し可能な環境を整える物件専用のゴミ置き場を用意すれば、このような問題が起こりにくくなるでしょう。
ゴミ回収業者の活用により、定期的にゴミを集荷してもらえます。
ゴミ回収・ゴミ集積所の管理などにコストはかかりますが、ゴミ屋敷ができるリスクを低くするだけでなく住人の暮らしやすさにも良い影響を与えます。
ゴミ屋敷のせいで被る損失を抑えるためには保険加入も効果的

ゴミ屋敷化した部屋の原状回復に必要なコストは、ゴミ屋敷の家主が払うものです。
しかし、「払えない」「払わない」行動に出る家主もいるでしょう。
家主が逃げてしまうなどの理由で、結果的に大家さんが修復費用を全額負担するケースも少なくないのです。
最悪の事態に備えて保険に加入しておけば、ゴミ屋敷の家主から原状回復費用が回収できない時の損失を抑えられるでしょう。
少額短期保険なら保険費用の負担を少なくできる
少額短期保険とは、文字通り少額かつ短い期間の保険を指し、「ミニ保険」と呼ばれることもあります。
保険料の負担が低い分受け取れる補償額にも限りがありますが、修繕費用の補償・第三者への賠償・大家さんへの賠償費用の補償などを対象とする保険なら、貸している部屋に何らかのトラブルが発生した場合の損失を補填できるでしょう。
ただし、対象になる事故の中に「ゴミ屋敷」が含まれることを確認してください。
ゴミ屋敷の住人と訴訟を起こす時の注意点
ゴミ屋敷の問題を解決しようと考えている大家さんは、事前に以下の注意点を知っておきましょう。
訴訟には多くのコストや労力がかかるため、十分な予備知識が必要です。
原状回復に必要な費用を全て訴訟で請求できるとは限らない
訴訟をすれば、ゴミ屋敷の住人に原状回復費用を請求できます。
しかし、原状回復費用は物件がゴミ屋敷になる前の状態に戻すためにかかる費用を指すわけではありません。
物件の経年劣化を考慮しなければいけないことから、原状回復費用全額は請求できないのです。
それでも、ゴミ屋敷になったことが原因だと言い切れる汚れ・破損を修復する費用は請求可能です。
裁判費用が用意できない時には法テラスを活用する
ゴミ屋敷の問題には悩んでいるけれど、裁判をする費用が用意できない大家さんは、「法テラス」を活用すると良いです。
法テラスでは、経済的に余裕がない方に向けての法律相談をしており、年収などの諸条件をクリアすれば、弁護士費用を安く抑えられる・分割払いできます。
裁判費用が用意できないからと言って、訴訟を諦めずに済むのです。
大家さんがゴミ屋敷の解決のために行ってはいけないこと

ゴミ屋敷は物件の所有者にとって重大な問題です。
火災などの多くのリスクが存在するだけでなく、物件の資産価値も下げてしまうでしょう。
しかし、大家さんは次のような行動をとってはいけないことを知っておいてください。
大家さんはゴミ屋敷のゴミを勝手に捨ててはいけない
大家さんはゴミ屋敷のゴミを勝手に捨てることができません。大家さんが入居者のものを捨てる行為は、所有権の侵害にあたるのです。
万が一、入居者が夜逃げした・孤独死した場合でも、大家さんが勝手に片付けをすることはできず、定められた手続きを踏んでから片付けをスタートします。
ゴミ屋敷の問題に頭を抱えているからと言って、独断での片付けは許されないと考えてください。
大家さんは共有部分にある私物も勝手に捨てられない
共有部分に置いてある私物であれば、処分しても良いのではないかと考える方は多いです。
しかし実際には、ゴミが置かれている・溢れている場所が共有部分でも、大家さんはゴミを勝手に処分できないのです。
他人の所有物を処分すると、権利の侵害として不法行為責任が問われる可能性があります。
大家さんはゴミ屋敷の住人に張り紙で注意喚起をしてはいけない
「ゴミ屋敷の住人に注意喚起をしたいけれど、なかなか本人を捕まえられない」
「注意喚起をしているのに問題を解決してくれない」
などの理由で、物件に張り紙をする大家さんもいます。
しかし、この行為は周囲の住人にゴミ屋敷の存在を伝えてしまう「名誉毀損」に該当する恐れがあるでしょう。
また、文面によっては家主に「大家から脅迫されている」と感じさせてしまう可能性も考えられます。
住人への注意喚起は、電話または郵便を活用するべきです。
大家さんは自力で退去を促す行為(嫌がらせなど)をしてはいけない
大家さんはゴミ屋敷の住人を追い出したいからと言って、電気・ガス・水道を止める・鍵を勝手に変えるなどの強引な手段を選んではいけません。
これらの行動は法律で禁止されており、大家さんが罰せられる可能性があります。
自力で問題を解決できそうもないと感じた時には、自治体や裁判所の力を借りるようにしてください。
ゴミ屋敷の原状回復に必要な費用の相場

ゴミ屋敷の住人が退去した後、大家さんは物件の状態を次の入居者が快適に暮らせるものに戻さなければいけません。
ゴミ屋敷の原状回復にかかる費用は物件の状態により異なりますが、以下を参考にしてください。
| 原状回復工事内容 | 費用 |
|---|---|
| 畳の張り替え(10畳) | 10万円程度 |
| クロスの張り替え(1部屋分) | 10万円程度 |
| フローリングの張り替え(10畳分) | 10万円程度 |
広い部屋の修復には50万円以上のコストがかかるケースもあるでしょう。
また、害虫・異臭・腐食などの問題を解決するためには、別途費用が必要です。
ゴミ屋敷の片付けや専門業者への依頼がおすすめ
ゴミ屋敷の片付けを専門とする業者は、ゴミの片付けや清掃に必要な知識と経験を使いスムーズにゴミ屋敷を美しくできます。
特に買取も依頼できる業者なら、片付けに必要な費用を買取で軽減できる可能性があるでしょう。
多くの業者では無料で見積もりを作成しているため、複数の業者から相見積もりをとってゴミ屋敷の片付けに最適な業者を見つけてください。
まとめ
物件がゴミ屋敷化すると、大家さんは火災・害虫・悪臭など多くのリスクを抱えることになります。
近隣住人からの苦情が集まるだけでなく、物件の資産価値が下がってしまう恐れもあるでしょう。
しかし、ゴミ屋敷の住人を追いやる・勝手にゴミを捨てるなどの行為は、法律で禁止されています。
この記事を参考に正しい手順を踏んで、ゴミ屋敷の住人に必要な原状回復費用を支払ってもらった上で、問題を解決できるようにしてください。
また、ゴミ屋敷が生まれてしまうことを予防するために、賃貸借契約時に特約をつけると良いでしょう。